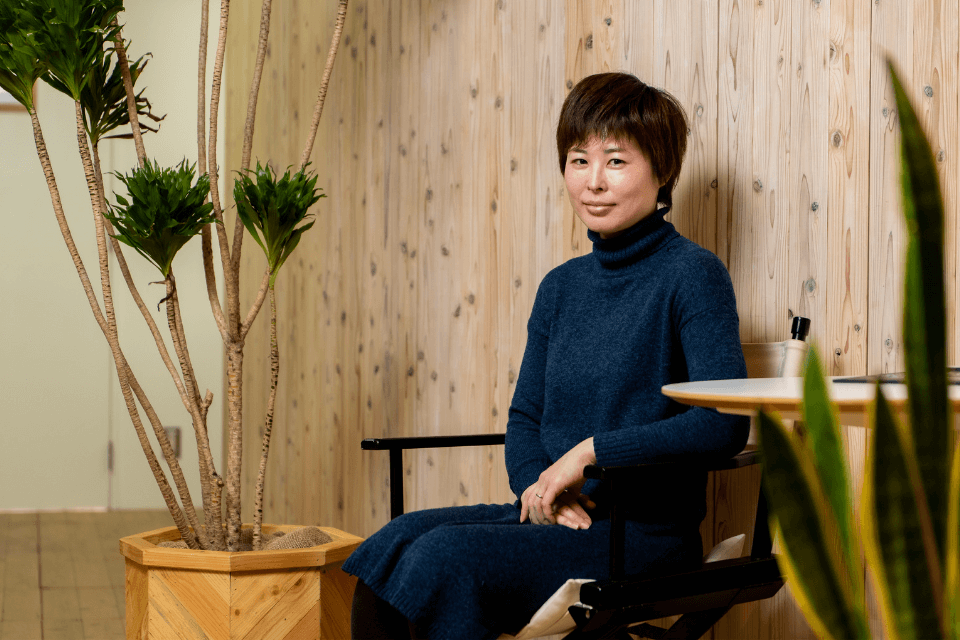PROFILE
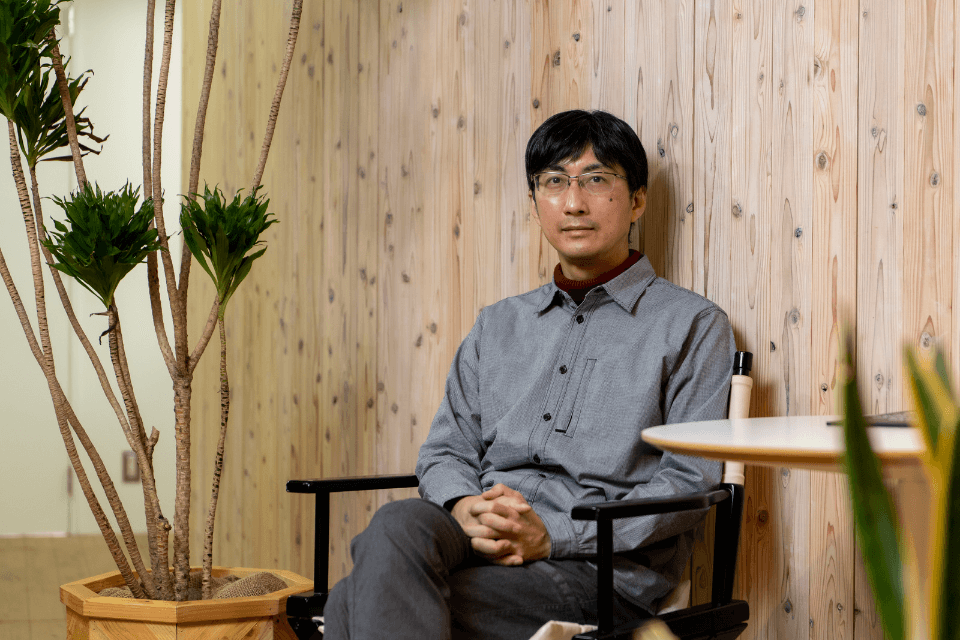
活躍の場が変わっても、データ分析と論理的思考が武器なのは変わらない
T.Y.
2014年12月入社
エンタテイメント・インサイト部/統括/CAO(Chief Analytics Officer)
大阪大学大学院にて物理学を研究し博士号を取得後、京都大学大学院にて研究活動を行う。2004年にアクセンチュアに入社。事業戦略、新規事業などに携わったのち、BtoC企業のマーケティング戦略に特化したコンサルティング会社の立ち上げに従事。その後、マクドナルド社の戦略・インサイトグループにて売上予測と利益向上の分析・示唆抽出を統括。GEM Partnersではデータインフラ戦略の実行、シミュレーションモデル及び分析・AI活用サービスの開発を担当している。
異色のキャリアの根底には一貫して「データ分析と論理的思考」がある
大学院で物理学の博士号を取得し研究職を経て、アクセンチュアに入社。その後、消費者向けデータマーケティングを経験し、GEM Partnersに入社しました。研究・コンサルティング・消費者向けマーケティング・エンタテイメント業界と、一見それぞれの仕事の関連性が薄く感じられるかもしれません。しかし、データを徹底的に分析し、論理的に考えて問題解決の糸口を見つけ出すというコアな部分は、キャリアを通して一貫していますし、私の一番の強みです。それまでのキャリアで磨いた分析のハードスキルは、入社後も非常に役立っています。
GEM Partnersに入社したのは、エンタテイメントのデータ分析という事業内容に惹かれたからです。もともと、エンタテイメントが好きなので、自分の培ってきたデータ分析やロジカルシンキングのスキルをベースに好きな業界に携わるチャンスだと思い応募しました。また、代表がマッキンゼー出身でコンサル業界を経験していて、自分のバックグラウンドと親和性が高いと感じたのも魅力的でしたね。
データと向き合い、エンタメの未来を創る

私は現在、CDO(Chief Data Officer)兼、エンタテイメント・インサイト部統括として、主に3つの役割を担っています。
1つ目は、データ分析基盤の構築です。エンタメ作品に関するデータ基盤を構築し、データ間の関連性を探るモデルや、ヒットを予測するモデルを開発しています。また、データ分析をさらに加速させるため、AIを活用した分析エージェントの開発も進めています。
2つ目は、グローバルな事業開発です。分析対象を海外に広げるため、国内外のパートナーと協力しながら、新たなサービスを企画・開発しています。
3つ目は、社員全体のスキルアップ支援です。部署の垣根を越えて、リサーチや分析に関するアドバイス、新入社員向けのロジカルシンキング研修などを実施し、会社全体の分析力向上に貢献しています。
「エンタメブランド」という概念を創り、事業を動かす
特にやりがいを感じているのは、エンタテイメントにおける「ファン」を分析する仕組みづくりです。
「IP(知的財産)」という言葉はありましたが、生活者の視点から見た「好きなエンタメのかたまり」を表す適切な言葉がなかったため、私たちは「エンタメブランド」という独自の概念を創り出し、そのファンを分析できる仕組みを構築しました。この取り組みは「推しエンタメブランドスコープ」などの商品として結実し、多くのクライアントにご活用いただいています。組織として積み重ねてきたデータやノウハウがあったからこそ、この仕組みを創り上げることができ、組織の継続的な成長を肌で感じられる、そんな瞬間に大きなやりがいを感じます。
データがもたらす、インパクトの大きさ
データ分析が事業に大きな影響を与えた、忘れられないプロジェクトがあります。
ある映画作品の興行収入目標は低かったのですが、調査・データ分析の結果、クライアントが想定していたターゲットとは異なる層にアプローチすることで、大幅な収益増が見込めることが判明しました。
この分析に基づき、ターゲットや訴求要素を見直す戦略を提案したところ、作品は100億円を超える大ヒットを記録しました。データ分析が、作品の成功を大きく左右することを実感した、貴重な経験です。
スキルアップを支える環境
当社は、データ分析力や提案の質をさらに高めるため、社員のスキルアップを積極的に支援しています。新入社員を対象としたロジカルシンキング研修もその一つです。グループワークを通して、論理的な思考力やアウトプットの仕方を身につけてもらうことで、誰もがスムーズに業務に取り組めるような環境構築に努めています。
優れた分析・戦略はフラットな組織から生まれる
マネジメントをするうえで大切にしているのは、フラットな組織づくりです。社歴や役職が違っても、役割の違いがあるというだけで、あくまで対等だと考えています。全員「さん」付けで呼ぶなど、上下関係を意識せず話ができる雰囲気づくりを心がけています。作品によってターゲット層が異なることもあり、エンタテイメントのマーケティングにおいて、若いメンバーの意見は非常に重要です。しかし、役職者はある程度の年齢であるケースが多いため、上下関係がはっきりしすぎていると、若いメンバーが発言しにくくなり、分析の視点が偏ってしまいかねません。
「エンタテイメントの元では、ファクトとインサイトの前では、全員がフラットである」という考えのもと、自由に発言できる組織にすることで、より的確な分析・提案ができると考えています。誰が言ったかではなく、何を言ったかが大切です。
より踏み込んだデータマーケティングが今後の目標
弊社では、これまで映画作品などの映像コンテンツをメインにマーケティングに取り組むことが多かったのですが、現在はそれも含みつつ「エンタメブランド」を軸にエンタテイメント全体の価値を最大化するための試みをしています。例えば、映画をヒットさせるだけでなく、マンガやゲーム、リアルイベントなどを含むコンテンツ全体の「ブランド」に対するファンへの理解を深め、ファン層を拡大していくための提案をしていくといった取り組みです。従来よりも大きな枠組みでファン心理や消費者心理を理解し、ニーズに合った派生コンテンツを供給することで機会損失を防ぎます。
さらには、近年のAIの発展を踏まえ、画像解析や施策・シナリオの自然言語分析といったクリエイティブそのもののデータ分析も進めたいと思っています。私の考えでは、マーケティングとクリエイティブの分析は、切っても切り離せません。
「エンタメブランド」の価値は、クリエイティブの魅力と消費者の反応の相乗効果で高まっていきます。その両者の関係性をより深く理解することが、価値の最大化につながると考えています。
2025年10月1日時点